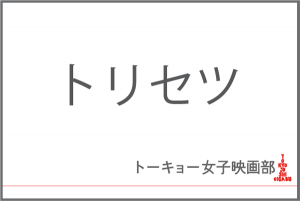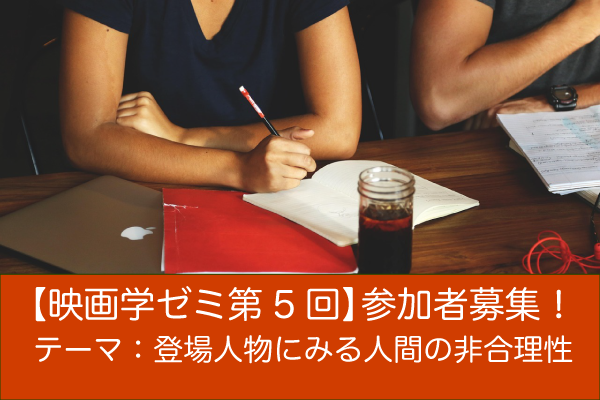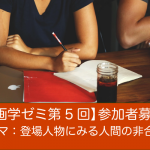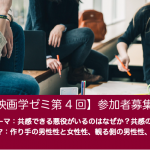前回の“移行対象”のお話の中で少し“愛着”について触れました。愛着(アタッチメント)とは「特定の人と結ぶ情緒的なこころの絆」(米澤好史 2020)と定義されていて、愛着形成の3つの基地機能として、安全基地、安心基地、探索基地という機能があるということをご紹介しました。今回はさらに“愛着”について掘り下げます。
※『MOTHER マザー』『タッチ・ミー・ノット~ローラと秘密のカウンセリング〜』のネタバレがあります。
問題の裏に見え隠れする愛着障害
愛着は赤ちゃんの頃から形成されていきます。愛着対象は母親であることが多いですが、限定されるわけではなく、父や祖父母などの養育者や身近な人も対象になります。このことについては後で触れますが、一旦ここでは母親が愛着対象として説明します。前述した愛着形成の3つの基地がちゃんと機能していると、子どもはお母さんの姿が見えなくても、何かあればきっと守ってくれると思って、安心して、友達を作ったり、いろいろなことにチャレンジしようという気持ちになれます。米澤好史(2020)は、安全基地、安心基地が形成されているかを知る子どもの行動として、こんな例を挙げています。
母と子が遊園地に遊びに来て、乗りたかった乗り物が見えてきた途端に子どもが母親の手を離して走って行ってしまいました。一見元気な子だなと思いますが、この行動からは、安全基地、安心基地は完成していないと考えられます。一方、子どもが母親に「行っていい?」と聞いた上で、母親が良いよと答えてから離れていったとします。一見、母親にお伺いを立てている消極的な子なのかなと思ってしまう人もいるかも知れませんが、これは母親が良いよというのがわかっていて確認しているのであり、母親を安心基地、安全基地だとして、そこから離れても大丈夫だと確認できたということになるのです。そして、安全基地、安心基地から離れて戻ってこれれば、探索基地が働く条件が整うとされています。
こういった愛着の基盤ができていると、成長するにつれて人間関係や接触する社会範囲が広がっても適応しやすいと考えられています。次に愛着理論を提唱したボウルビィとともに、愛着についての研究を行っていたエインズワースによる、愛着の個人差を調べる“ストレンジ・シチュエーション法”をご紹介します。丹野義彦、石垣琢磨ほか(2018)によると、この実験では、子どもは母親を実験室に入り、見知らぬ人に預けられます。母親はしばらくしたら戻ってきます。こうした分離と再会の場面における子どもの反応を分析するのが“ストレンジ・シチュエーション法”です。下記に4タイプを記します。
■A回避型:親との分離時に、泣いたり混乱したりすることがほとんどなく、再会時には親から目をそらしたり、親を避けようとする行動がみられる。親を安全基地として室内の探索を行うことがほとんどない。
※回避型の子どもの親は子どもの働きかけに対して、拒否的にふるまうことが多い。また母親は子どもの行動を統制しようとして働きかけることが多い。
■B安定型:親との分離時に多少の泣きや混乱を示すが、再会時には積極的に親に対して身体的接触を求め、簡単になだめられる。親や見知らぬ他者からの慰めを受け入れやすく、親や活動拠点として積極的に探索活動を行う。
※安定型の子どもの親は、子どもの要求に対して、タイミングよく応答し、行動が一貫しているため、子どもは親に対して強い信頼感をもつことができる。
■C不安・抵抗型(アンビバレント型):親との分離時に非常に強い不安や混乱を示し、再会時には強く身体的な接触を求める。一方で、親に対して怒りを示し、激しく叩いたりする。行動が不安定で用心深く、親に執拗にくっついていようとすることが多い。
※アンビバレント型の子どもの親は、子どもの要求に対して、応える時とそうでない時があり一貫しておらず、応答のタイミングもずれることが多い。
■D無秩序・無方向型:近接と回避という本来ならば両立しない行動を見せる。どこへ行きたいのか、何をしたいのかきわめて読み取りづらい。
※このタイプの子どもの親は、抑うつ傾向が高いことや、精神的に極度に不安定であること、日頃から子どもを虐待するなどの兆候が多く認められている。
[無藤隆、若本純子、小保方晶子(2014)]
さらに、無藤隆、若本純子、小保方晶子(2014)は、被虐待児を対象にした研究では、そのうちの8割から9割が無秩序・無方向型に占められるという見方があることを提示し、養育者が脅え、脅えさせるように子どもにふるまう時、子どもは本来ストレス下でやすらぎを得るべき相手から保護を得られず、脅えさせられるという恐ろしいパラドックスの中におかれ、結果として愛着行動が無秩序になると分析しています。さらに、無秩序・無方向型の乳児の愛着は、3歳頃から徐々に親子の立場が逆転したような養育者に過度に世話を焼くような行動や、懲罰的な態度などからなる統制的な愛着行動へ移行しはじめるとしています。

ここで映画『MOTHER マザー』について考えてみます。本作は、2014年に埼玉県川口市で起きた実際の事件を取材した山村香著のノンフィクション「誰もボクを見ていない:なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか」(ポプラ文庫)を原案にしたフィクションです。実話を基にしたフィクションということを踏まえた上で、映画の中のキャラクターについて考察します(ですので、実在の人物の分析ではありません)。母、秋子と、息子、周平は、周平が秋子の面倒を見ているような関係で、周平は母から離れたがっているように見える時もありますが、実際はそのチャンスがあっても離れようとしません。これは前述の“無秩序・無方向型”の子どもの特徴と何となく繋がります。冒頭のシーンを観ると、秋子が息子を溺愛しているように思いますが、日常が見えてくると、愛情なのかただの依存なのかがわかりません。秋子は働こうとせず、パチンコに散財し、お金がなくなれば家族に金をせびり、断られると周平を金の無心の道具に使ったりして、社会的な活動や親としての活動には無気力です。また気性が荒く、人の親切を仇で返すようなことも平気でやります。映画の中の様子だけでは断定できませんが、鬱っぽい様子もうかがえるし、反社会性パーソナリティ障害の要素も感じられます。
周平がまともな環境で育てられなかったことは十分に伝わってくるので、何らかの精神的問題を抱えていても当然だと思いますが、気になるのはむしろ母親の秋子で、結論から先にいうと、周平よりもむしろ秋子に愛着障害があったのではないかということです。彼女がなぜあんな風になったのかを考える際、まずは秋子と家族との関係に目がいきますが、父、母、妹はいたって普通で問題があるようには見えません。ではなぜ秋子だけが…ということになりますが、ここで愛着の話に戻します。
米澤好史(2020)によると、“愛着障害”を引き起こす要因として誤解がある事柄の一部として「産んだ母親のせい」「育て方の問題」「親の養育を受けられない、親から虐待を受けた」ということが挙げられます。でも実際は、愛着対象は母親に限らず、他の養育者や第三者も愛着対象になり得ます。そして、育て方の問題「どう関わったか」ではなく、子どものほうが「しっかりと関わってもらった」と感じるかどうかが重要なのです。
だとすると、母親は一生懸命育てたつもりでも、秋子は「しっかりと関わってもらった」と感じないまま育った可能性があります。そのヒントは序盤の秋子の実家のシーンで、母親が妹ばかりかわいがっていると秋子が訴えるところにあります。これはお金を貸してくれないことに対するただの文句にも受け取れますが、もしかしたら姉としてはまだ甘えたい時期に妹にお母さんを奪われたような感覚でずっといたのかも知れません。さらに気になったのは、周平が1人で秋子の実家に行きお金を貸してと頼んだ時、祖母(秋子の母親)が怒り狂って孫の周平にそのまま感情をぶつけたところです。秋子に怒るのは無理もないですが、まだ幼く罪もない孫に対しての反応としては少し異様です。そういったシーンからの憶測でしかありませんが、祖母にも少し気性が荒いところがあり、秋子の面倒をみる時は1人目で子育てに慣れておらず、秋子に少し不安定に接していたのかも知れません。
米澤好史(2020)では、愛着の世代間伝達は自動的には起こっていないことが調査からわかったと記されていて、そうであれば、単純に秋子から周平に愛着障害が伝達したのではないと考えられます。でも、米澤好史(2020)に記されている「親が子どもを育てるとき、自身の親(子どもにとっては祖父母)がもう一度影響を与え、子育てに関して“こうしろ”“こうしてはいけない”と指示して親を傷つける、あるいは傷つけられると脅威に感じることがいちばん強く媒介していたのです」という点から考えると、前述の実家のシーンで秋子の家族が揃うなか、周平の目の前で秋子が責められている状況なども、周平にとってはかなりのダメージだった可能性があります。この2人のキャラクターについては、簡単に分析できるものではなく、この記事だけで完結できませんが、また新たな視点が出てきたら考えてみたいと思います。

そして、愛着障害という観点から観て欲しい映画がもう一本、『タッチ・ミー・ノット~ローラと秘密のカウンセリング〜』です。これは触れられることに拒絶反応が出てしまう女性が主人公のストーリーです。内容についてはレビューをご覧頂ければと思いますが、最後の監督の独白のところで、まさに愛着について語られています。映画の冒頭から、監督が誰かに向けたメッセージを独白している部分があるのですが、最後まで観ると、それが母親に向けられたものだとわかります。ここで誤解して欲しくないのは、先ほどの誤解例でも触れましたが、愛着の問題はすべて母親の責任ということではないということです。ただ、ほとんどの赤ちゃんは母親との1対1の関係から人間関係が始まり、それがその後の人間関係や活動の基盤になるので、それだけ影響が大きいということです。『タッチ・ミー・ノット~ローラと秘密のカウンセリング〜』には、母親というキーワードはあまり出てきませんが(敢えてそうしているのだと思います)、主人公が自分の精神疾患をどう手放していくのかを追うなかで、愛着とは何ぞやというのを映し出しています。
今愛着障害の子どもが増えているようで、「発達障害ではないと診断されたのにどうしてこんなこと(問題行動)をするんだろう?」と悩む親御さんもいらっしゃるようです。ちなみに米澤好史(2020)は発達障害と愛着障害が併せもつケースもあり、愛着障害もスペクトラム(同じ線上にあるが程度の差があるということ)で捉えるという考え方を提唱しています。今まで私は、母と子の話、子どもの話を描いた作品を愛着という視点で観たことはありませんでしたが、改めて愛着の視点で観ると何か気付きがあるかも知れません。でも、決めつけたり、勝手に妄想を膨らませて悩みを大きくして欲しくはないので、実際に子育て中で気になることがあったら、適切な相談先を見つけて話してみてください。
<参考・引用文献>
米澤好史(2020)「やさしくわかる! 愛着障害」ほんの森出版
無藤隆、若本純子、小保方晶子(2014)「心理学の世界 基礎編5 発達心理学 人の生涯を展望する」培風館
丹野義彦、石垣琢磨、毛利伊吹、佐々木淳、杉山明子(2018)「臨床心理学」有斐閣

『MOTHER マザー』
2020年7月3日より全国順次公開
REVIEW/デート向き映画判定/キッズ&ティーン向き映画判定
秋子は本当に酷い仕打ちを周平にしますが、彼女をただ酷い親、ダメな親だと片付けてしまいたくありません。周平はとても素直で性格も良く、頭も良いので、どこかで救えていれば全然違った人生を歩んでいたと思います。問題を抱える子どもについて、本人だけでなく、家族、周囲についても、何が起きていたのか考える必要があると感じさせられたストーリーです。
© 2020「MOTHER」製作委員会

『タッチ・ミー・ノット~ローラと秘密のカウンセリング〜』
2020年7月4日より全国順次公開
R-18+
REVIEW/デート向き映画判定/キッズ&ティーン向き映画判定
肌に触れるということは、自分の存在や、自分以外の人の存在を感じられる行動であり、愛着の観点からしてもとても重要な行動です。前回の“移行対象”のところでも取り上げましたが、スキンシップという言葉が生まれたように、肌を触れあうという行為が意味するものはとても深いです。公式サイトに監督の解説があるので、ぜひそちらも読んでみてください。
©Touch Me Not -Adina Pintilie
『愛を乞うひと』
Amazonプライムビデオにて配信中(レンタル、セルもあり)
DVDレンタル・発売中
なぜそんなにされてまで…と悲しくなりますが、子どもの母への思いの大きさを実感します。
TEXT by Myson(武内三穂・認定心理士)