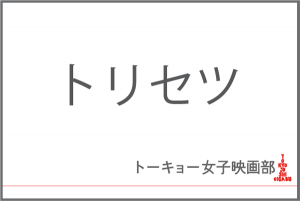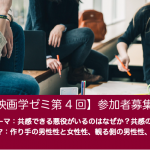『宝島』
2025年9月19日より全国公開
監督:大友啓史
出演:妻夫木聡/広瀬すず/窪田正孝/永山瑛太
配給:東映、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
公式サイト
REVIEW/デート向き映画判定キッズ&ティーン向き映画判定 沖縄がアメリカ統治下だったことについてどう思う?『宝島』アンケート特集 映画の力を信じている『宝島』完成報告会見にて、妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、大友啓史監督が語った熱い思い
『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド&バタフライ』などを手掛けた大友啓史監督が<沖縄がアメリカだった時代>を描いた映画『宝島』。今回、当部の部活史上初めて監督ご本人にご参加いただき、映画好きの皆さんと一緒に本作について語っていただきました。熱い想いが詰まった貴重なお話をたくさんお聞きできたので、前編と後編に分けてお届けします。
【トピック一覧】
前編
当時の沖縄とピュアに向き合うためには、商業的な逆算はいらない
本土復帰前の沖縄の話をいつか絶対にやりたいと思っていた
沖縄のソウルと沖縄の立場から作る映画
当時の沖縄の方達の気持ちを追体験して欲しい
想像力だけが他者に起きた出来事を共有するために私達に与えられた武器
後編
不当に尊厳を奪われれたら、声を上げるのが当たり前
皆さんにとっての宝は何ですか?
当時の沖縄とピュアに向き合うためには、商業的な逆算はいらない

マイソン:
トーキョー女子映画部の部活としては監督にご参加いいただくのは初めてです。ありがとうございます。本日はよろしくお願いします!
大友啓史監督:
今日はぜひ部活に参加させてください!
マイソン:
さっそく順番に感想や質問があればお願いします。
Aさん:
めちゃめちゃおもしろかったです。今年は終戦80年ということで、最近『雪風 YUKIKAZE』も観たのですが、戦争とは何か考えていました。私の世代はあまり戦争に対して興味を持つ方がいなくて、観るのは小説や映画なので、この映画は今の若い方達というか、小学生とかにも見せていいんじゃないかと思いました。小さい時にこういう作品を観るか観ないかとでは全然違ってくるとすごく感じました。
Cさん:
とてもおもしろかったです。3時間ちょっとあるのにあっという間でした。私は役者さん同士のアクションシーンで下からのカメラアングルが印象的でした。それがとてもリアルで、殴られた人が本当に転がってきたように感じました。
Dさん:
戦後の沖縄の実態を描いた映画で3時間というと少し身構えてしまう人もいると思いますが、本当にあっという間で、監督の作品は他の作品も含めて眠たくなることがありませんし、中だるみもない、本当に監督だからこそできる作品だと思います。歴史を扱う作品なら大友監督だと思うので、今後の作品も楽しみにしています。
Eさん:
戦争のことは、今までもいろいろな映画を観てきたので、知っているような気がしていたんですけど、沖縄について実はあまりよくわかってなかったなと思いました。観ていてすごくリアルに感じて、本当に観る価値のある映画だと思いました。ちょっと失礼な質問かもしれませんが、190分の上映時間は業界的にも敬遠されると聞いたことがあります。元々190分くらいの脚本を作ろうと思っていたのか、編集の段階でこれだけ良い画が撮れているから残したいと思って190分になったのか、お聞きしてもよろしいでしょうか?

大友啓史監督:
歴史というのは、物語の「ただの背景」ではありません。それぞれの人物はその人が生きた時代に、決して切り離された「個人」として存在しているわけではなく、その時代の有り様に確実に影響されて生きているのだと思います。生まれたタイミング、時代、国、環境。僕らは本当に平和な国、たまたま戦争がないタイミングで生まれたから、すごくラッキーとしかいいようがありません。そう考えると、題材によって、そして描く物語の舞台によっては、歴史の厚みを描くことが人間ドラマを描くうえでもとても大切だということになります。人物のキャラクターの立ち位置を明確にしたり、よりその物語を観客が理解する手助けにもなるということですね。今回の「宝島」は、映画を作るために映画を作るのではなくて、伝えたいことが明確にあって作った作品です。世の中にきちんとした形で、伝えたいと思うことを過不足なく伝えたい。当初僕が映画会社に持っていったのは5時間近い分量の企画でした。
一同:
お〜!!
大友啓史監督:
あの原作の分厚さと、沖縄の20年の歴史を描くのに5時間と考えると、長いと思いますか?
一同:
長くはないですね。
大友啓史監督:
そうでしょ?でも、5時間で配給会社に持っていった時に、「いやいや、それをやられたら僕らは全員クビですよ」と、怒られました(笑)。
一同:
ハハハハハ!
大友啓史監督:
そりゃそうですよね(笑)。撮影中も撮っている量が多かったので、妻夫木くんは6時間の映画になるんじゃないかと言っていたけど(笑)、最初のラッシュで3時間20分になりました。3時間の映画の場合劇場で上映できる回数が限られてしまう可能性があるので、一般的にプロデューサーも配給も皆嫌うんですよね。だから僕は当然皆がイエスと言うとは思っていませんでした。どうせ切れって言ってくるんだろうと(笑)。そしたら誰も短くしようと言わなかったんで、こちらがびっくりした(笑)。
一同:
お〜!!

大友啓史監督:
普通なら絶対にこの段階で短くして欲しいと議論になるんです。この尺でOKと言われて、逆に僕がビビッってしまったんですね。まだCGも入れていなくて、音楽も仮、セリフも整音されていないタイミングだったのですが、皆さん「すごくいい!」「全然時間を感じない」と。その後も、そういう経緯を数度経て、今はファストムービーの時代だけど、だったら真逆を行こうと皆で覚悟を決めたんですね。プロモーション優先の発想をしない、主題歌を使わないなど、とにかく当時の沖縄とピュアに向き合うために、商業的な逆算はすべて捨てようと、最初からそういうつもりではいたのですが、これでとうとう腹が決まったというか。僕が日本人を代表するつもりはありませんが、あの時代の沖縄のことを何も知らなかった僕ら本土の人間は、ある意味贖罪の意も兼ねて、それぐらいのリスクを背負うのは当然だろうと、そんな気すらしていたんですよね。
本土復帰前の沖縄の話をいつか絶対にやりたいと思っていた

Gさん:
戦後の沖縄がアメリカに占領されていた時の話だということで、最初はすごく身構えていて、何か急に残酷な描写があるのかと思っていましたが、ちょっとクスッと笑えるようなナレーションがあったり、とてもおもしろくて興味深い内容でした。
私達は戦後に生まれて、沖縄の本土復帰のことは『ちゅらさん』で知った世代なので、ここまで別物だったということがやっと今身に染みた気がします。祖母から「沖縄は本土復帰前、パスポートがないと行けなかったんだよ」と聞いたことがありましたが、正直沖縄のことを当時ないがしろにしていたくせに、今は観光地として沖縄をヨイショしていることに、すごく複雑な気持ちになりました。この映画を観ると、小学校に戦闘機が落ちることの怖さをリアルに感じられ、実際にこういう事件があったからこそオスプレイの飛行を反対していた意味がわかりました。
大友啓史監督:
そうなんですよ。
Gさん:
監督にお聞きしたいのが、NHKは他の局に比べてドキュメンタリーなどで戦時中や戦後をテーマにした番組をやっていると思うのですが、そういった影響もこの映画に表れているのでしょうか?
大友啓史監督:
確実にあるとは思います。NHK時代に撮っていた『ちゅらさん』の主人公は、アメリカの統治が終わって復帰した年に生まれた“復帰っ子”でした。ですから『ちゅらさん』の場合は、復帰前の歴史には触れてはいない。一方で、当時このドラマの取材をしていた頃から、沖縄の方達の大きな優しさの中にある「強さ」を幾度となく感じていました。「なんくるないさ」という言葉がありますが、それは、「ここから先は譲れない」というものをきちんと持っているゆえの言葉であって,根底にはきっと、復帰前のコンディションや歴史が影響しているんだろうと。なので、『ちゅらさん』を撮っていた時から、僕は復帰前の沖縄の話をいつか絶対にやりたいと思っていたんですね。2019年にこの原作に出会って、「やりたかったのはこれだ!会いたかったのはこれだよ!」と。アメリカ統治下、復帰前の沖縄をちゃんと描かないと、沖縄とちゃんと向き合ったことにならないんじゃないかと、ずっと抱いていた想いが一気に線として繋がった瞬間でしたね。
沖縄のソウルと沖縄の立場から作る映画

Fさん:
私は敢えて時代背景を勉強せずに臨んだのですが、大変おもしろかったです。場面が切り替わる時に年代が出てくるので変化がわかりやすかったですし、登場人物達の爪や歯、髪質などの容姿の変化もおもしろくて、たくさん楽しめた3時間でした。1つ伺いたかったのが、沖縄は方言が強い印象があるのですが、セリフでは方言っぽいものと標準語っぽいものがあり、使い分けてらっしゃるのかなと思いました。そのこだわりは何かありますか?
大友啓史監督:
『ちゅらさん』のように朝ドラの場合は半年ぐらい放送する間に、視聴者も耳慣れて定着していく方言がいっぱいあるんです。ところが映画の場合はそうではないので、方言がわからないことで観賞を妨げられることがないようにしなくてはいけません。例えば冒頭の追われて森の中に逃げるシーンは、方言がわからなくても、2人がパニックになっていることはわかりますよね。そういう状況での沖縄弁は、その内容がはっきり識別できなくても、ある程度観ている方も許容してくれるんじゃないかと思いました。一方、芝居でちゃんと感情を伝えるシーンでは、状況ではなくて、気持ちが伝わるように丁寧な、伝わりやすい方言にしています。
試写をやっているなかで方言がわからないと乗れないという意見もやっぱりあったんです。それでテロップとか、いろいろなことをトライしたのですが、標準語に翻訳して字幕を出してしまうと、一気にアメリカ統治下の沖縄という時代感が薄れ、追体験としての、映画への没入感が弱まってしまう。字幕があることで客観的になってしまい、ふと現実に戻されてしまうんですよね。どちらが良いか何度も慎重に議論を重ね、結局字幕を入れることはやめました。上映時間の話と同様に、やっぱりお客さんに観てもらうための最低限のラインとせめぎ合いながら、今の形に何とかたどり着いたんです。
当時の沖縄の方達の気持ちを追体験して欲しい

Bさん:
私は鑑賞直後でまだ受け止めきれていないのですが、本当に時代感や世界観の壮大さに圧倒されて、現実なのかフィクションなのかわからなくなりました。最後のエンドロールを観て、これは現実にあったことなんだと改めて実感しました。監督が映画を作る上でフィクションとリアルの境という点について意識されたことは何かありますか?
大友啓史監督:
今はバーチャルな世界観が当たり前のように世に溢れていますが、フィクションをリアルに感じることで、リアルとバーチャルの境目がどんどんなくなってきていますよね。たぶんテレビを観て育った僕らの世代がそういう第1世代のような気がします。自分の手で触って届くところにあるものに名前があり、それに触れて「これはリンゴだ」「電話だ」「机だ」と覚えていくのが人間の認識の始まりだそうです。ところが、テレビなどの映像というのは、映像の中のモノには、手を触れることができない。例えば画面に人が映っていても、実際にその人に手は届きません。
触覚の初期認識が、人間の認知に大きな影響を与えているとしたら、映像はもしかしたら人間の認識の在り様に、長期間に渡って何か大きな変化を与えてきたのではないかと思っているんですね。ちょっと、すごく深い質問をしていただいて困っていますが…。
一同:
ハハハハハ!

大友啓史監督:
例えば映画で同じ戦争ものを観るにしても、もしかしたら遠い外国の戦場の、外国人同士の戦闘シーンのほうが、我々にとっては、多少なりとも、痛みが少なく感じられるかもしれません。これは、同じ文化圏に生きる人間か、同じ民族かどうかといったような、自己を投影できるそういう部分の質量の違いが、映像を見るときの当事者感覚として、大きな相違をもたらすのではないか、という議論です。一方で、例えば『プライベート・ライアン』の冒頭のように、そのあまりに容赦ない描写に、誰もが同じような痛みを感じ取らざるを得ない作品もある。そう考えると、映像に触れる時に、そして、その映像がどれだけ観た人のリアリティーに影響を与えるかというときに、個々の人生経験に基づく認識論や当事者感覚というのがすごく影響してくると思っていて。
いつも僕はどこかで観客に、物語の中の当事者のように感じて欲しいと願って作っているんですね。観ている方が「いい映画だったね」というだけではなくて、物語に参加しているような、当事者として映画を共有できるようにするにはどうしたらいいのかということを、映画作りとはまた別のスタンスで考えていて。
この映画で描かれているアメリカ統治下の沖縄について、僕らは本当に何も知らないですよね。一方でその時代は、日本本土は高度経済成長期で一番勢いがあった時代です。日本国憲法が新しく施行され、自由主義、民主主義、平等、個人の尊厳、公共の福祉、そういう法律上の概念で人々は守られるようになり、堂々と豊かさを追求することができた。東京オリンピックや大阪万博の開催、東京タワーができて、というようにすごく良い時期だったのに、戦争で日本の防波堤となり県民の4人に1人が亡くなった沖縄、今でも基地の7割がある沖縄は、当時アメリカの統治下にあり、日本の憲法が適用されず、アメリカのルールの元で様々な不条理に苦しんでいた。そう考えると、沖縄の方達がどういう想いを持ってあの日常を生きていたのかを知らない限り、今に続く沖縄の方達の本当の思いを理解することは難しいように思うんですね。だったら、せめてこの映画で、その時代の沖縄の方達の気持ちを追体験したいなと、もちろん僕自身も含めて、そう思ったんですね。
想像力だけが他者に起きた出来事を共有するために私達に与えられた武器

マイソン:
沖縄の映画は沖縄の方が撮り、沖縄の方が出演するほうがよいのではないかという意見の方もいそうですが、今お話をお伺いしていると、沖縄出身ではない方が監督、出演するからこそ追体験になるという意図がおありだったのかなと思いました。
大友啓史監督:
演技の本質というのは、相手のことを理解し、演じるプロセスを通して、一生懸命その人になりきる、相互理解のコミュニケーションなのだと思います。演じることによって当事者の方達の感情を知る。役者達も追体験するんですよ。一生懸命あの時代の沖縄の人になって生きようとした時に、身に降りかかってくることは何なのかと。他者に起きた出来事を自分の体験や痛みとして埋めていくことこそが想像力で、想像力こそが他者に起きた出来事を共有するために私達に与えられた武器なんだと思う。そうやって生まれた作品を通して、さらにお客さんたちにも、あの時代の沖縄で生きた人々の感情を追体験してほしいと思っていて。
マイソン:
ここまでお話をお聞きして、『宝島』までの道のりは、NHK時代、映画監督になってからと、大友監督のキャリア全部に繋がっていると感じました。
大友啓史監督:
そうかもしれませんね。僕はNHK時代に初めて秋田局に赴任して、上司に「声にならない声をちゃんと伝えることが、我々ジャーナリズムの仕事なんだよ」と言われて、すごく感動したことを覚えています。「映画」に関する教えではないんですけどね、それが僕のルーツになっているのは間違いないと思います。
座談会の後編(2025年9月12日UP)では、トーキョー女子映画部で事前に行ったアンケート結果を基にディスカッションをした内容を掲載します。

『宝島』
2025年9月19日より全国公開
監督:大友啓史
出演:妻夫木聡/広瀬すず/窪田正孝/永山瑛太
配給:東映、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
公式サイト
REVIEW/デート向き映画判定キッズ&ティーン向き映画判定 沖縄がアメリカ統治下だったことについてどう思う?『宝島』アンケート特集 映画の力を信じている『宝島』完成報告会見にて、妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、大友啓史監督が語った熱い思い
沖縄がアメリカだった1952年。幼馴染みのグスク、ヤマコ、レイ、オンは、いつか大きな戦果を上げることを夢見ていた。そしてある襲撃の夜、オンは“予定外の戦果”を手に入れ、突然消息を絶ってしまう。残された3人は、オンの影を追いながらそれぞれの道を歩み始める。しかし、何も思い通りにならない現実に、やり場のない怒りを募らせ、ある事件をきっかけに抑えていた感情が爆発する。消えた英雄が手にした“予定外の戦果”とは何だったのか?そして、20年の歳月を経て明かされる衝撃の真実とは?
ムビチケ購入はこちら
映画館での鑑賞にU-NEXTポイントが使えます!無料トライアル期間に使えるポイントも
©真藤順丈/講談社 ©2025「宝島」製作委員会
2025.8.19 event
本ページには一部アフィリエイト広告のリンクが含まれます。
情報は2025年9月時点のものです。最新の販売状況や配信状況は各社サイトにてご確認ください。